最近、野菜の価格が高騰し、食卓への影響を感じることも多いですよね。そんな中、春の訪れとともに八百屋やスーパーの店頭で見かけるようになるのが「たけのこ」です。独特の香りと食感で、春を感じさせてくれる代表的な味覚の一つ。
この時期(4月末~5月)には、旬を迎えた「孟宗竹(もうそうちく)」などのたけのこが市場に多く出回り始めます。加工されたたけのこ(水煮など)も通年手に入りますが、やはりこの時期ならではの掘りたての風味は格別です。
せっかく手に入れたたけのこ、アク抜きなどの下処理が必要な場合もありますが、ポイントを押さえれば、無駄なく美味しく食べられます。今回は、美味しいたけのこの選び方、長持ちさせる保存方法(下処理後)、そして定番から意外なものまで美味しい調理法をご紹介します。
美味しい「たけのこ」の選び方
たけのこは種類や状態によって、味や食感が大きく変わります。新鮮で美味しいたけのこを見つけるためのポイントを見ていきましょう。(※主に、この時期出回る孟宗竹などを想定しています)
- ずんぐりとして、重みがあるものを選ぶ 見た目が太く短く、ずんぐりとした形をしていて、手に持った時に重みを感じるものを選びましょう。水分をしっかり含んでいて、中身が詰まっている証拠です。細長いものより、丸みがある方が柔らかい傾向があります。
- 皮の色と状態をチェック 皮は、薄い茶色(または品種により黄色みがかっている)で、ツヤがあり、しっとりしているものが新鮮です。穂先(先端)まで皮がしっかり巻いていて、乾燥していないか確認しましょう。黒いシミが少ないものが良いです。
- 穂先の色を見る 穂先(先端)の色が濃い緑色ではなく、黄色っぽいものがおすすめです。緑色が濃いものは、地面から出て日光に当たりすぎた可能性があり、アクが強く硬いことがあります。
- 切り口(根元)を確認する 切り口が白くてみずみずしいものが新鮮です。時間が経つと乾燥してきたり、変色したりします。根元の「赤いブツブツ」が少ない方が、アクが少ないと言われています。
- 節(ふし)の間隔もチェック 節と節の間隔が極端に広すぎないかもチェックしましょう。間隔が広すぎるものは成長しすぎて硬い場合があります。ただし、硬さやアクの強さはこれだけで決まるわけではないので、最優先は全体の形や重さ、切り口の新鮮さなどで総合的に判断するのがおすすめです。
【重要】たけのこの保存方法(アク抜きが前提!)
生のたけのこは時間との勝負です!収穫後、時間が経つほどアク(えぐみ)が強くなるため、入手したらすぐにアク抜きをするのが美味しく食べる最大のコツであり、保存の第一歩です。
- アク抜き方法(孟宗竹などの場合):
- たけのこの皮を2〜3枚むき、先端を斜めに切り落とし、根元の硬い部分を少し切り揃える。皮に縦に1本切り込みを入れる(火の通りを良くし、皮をむきやすくするため)。
- 大きめの鍋にたけのこ、たっぷりの水、米ぬか(一掴み程度)、赤唐辛子(1〜2本)を入れる。
- 落し蓋をして、中火〜弱火で1時間〜1時間半ほど、根元に竹串がすっと通るまで茹でる。
- 火を止めて、茹で汁ごと完全に冷ます。(時間をかけて冷ますことでアクが抜けやすくなります)
- アク抜き後の保存:
- 冷めたら皮をむき、水洗いする。
- 密閉容器に入れ、たけのこが完全に浸るように水(茹で汁ではなく)を注ぎ、冷蔵庫で保存する。
- 毎日水を替えれば、4〜5日程度は保存可能です。
- 冷凍保存: 使いやすい大きさに切り、水気をよく拭き取ってから冷凍用保存袋に入れて冷凍。ただし、食感が少し変わるため、煮物や炊き込みご飯などに向きます。
たけのこを美味しく食べる調理法
アク抜きさえ済めば、たけのこは様々な料理で楽しめます。
- たけのこご飯 (定番中の定番) たけのこの風味と食感を存分に味わえる炊き込みご飯。油揚げや鶏肉と一緒に炊き込むと、さらに旨味が増します。
- 若竹煮 (春らしい煮物) わかめと一緒に、だしで煮含めた優しい味わいの煮物。たけのこの穂先を使うと柔らかく仕上がります。
- 土佐煮 (しっかり味) 鰹節をたっぷり使い、甘辛く煮付けたご飯が進む一品。お弁当のおかずにも。
- 天ぷら (食感を楽しむ) 薄切りにして揚げるだけ。サクッとした衣と、たけのこの食感が楽しめます。穂先も根元も美味しいです。
- 炒め物 (中華風など) 豚肉や他の野菜と合わせて、オイスターソースなどで炒めると、ご飯にもお酒にも合う一品に。
- 焼きタケノコ (香ばしさを楽しむ) アク抜きしたたけのこを適当な大きさに切り、グリルや網で焼きます。醤油や味噌を塗って香ばしく仕上げるのもおすすめです。
たけのこに関する豆知識
知っているとちょっと自慢できる?たけのこトリビアをご紹介!
- 驚異の成長スピード!「筍」の由来 たけのこ(筍)の字は「竹」かんむりに「旬」。これは、旬の時期(10日間)であっという間に竹に成長する、その驚異的な成長スピードを表しています。種類によっては1日で1メートル以上伸びるものも!
- 白い粉は旨味成分! (※アク抜き後の注釈で説明済みですが、豆知識としても再掲)茹でた後に出てくる白い粉はアミノ酸の一種「チロシン」。旨味成分であり、食べても問題ありません。
- 栄養も意外と豊富! 低カロリーで食物繊維が豊富なほか、体内の余分な塩分を排出するカリウムも含まれています。むくみ予防や高血圧予防にも役立つとされています。
- 日本古来の食材 たけのこは縄文時代の遺跡からも見つかっており、古くから日本人に親しまれてきた食材です。春の山の恵みとして大切にされてきました。
まとめ
春の訪れを告げる味覚、たけのこ。アク抜きなど少し手間はかかりますが、その独特の風味と食感は格別です。野菜高騰の折、旬の味を上手に取り入れて、食卓を豊かにしたいものですね。 ぜひこの時期ならではの、新鮮なたけのこを味わってみてください。

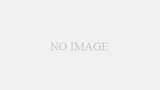
コメント