「もっと強く、もっとたくましくなりたい!」 トレーニングに打ち込む多くの人が、熱い思いを持っていますよね。僕もその一人です。しかし、その情熱が時に、予期せぬ怪我という形で現れることがあります。
今回は、僕自身がトレーニング中に経験した「肩の痛み」について、その原因として考えられること、関連する肩周りの筋肉、そして同じような怪我を防ぐために本当に大切なことを、体験談を交えながらお伝えしたいと思います。
始まりは突然の痛み…プレス系トレーニングでの異変
いつも通りジムでトレーニングに励んでいたある日、ベンチプレスやショルダープレスといった、いわゆる「プレス系」の種目をこなしている最中に、肩に嫌な痛みを感じるようになりました。「ズキッ」としたり、動かしにくかったり…。
「気のせいかな?」とも思いましたが、痛みを抱えたまま続けるのは明らかに良くない。その日はプレス系を諦め、比較的痛みを感じなかった「フライ系」の種目に切り替えました。これが、自分の肩と向き合うきっかけになるとは、その時は思ってもいませんでした。
肩のゴリゴリ音と特定の動きでの痛み…これは一体?
フライ系は大丈夫そうでしたが、日常生活でふと腕を上げ下げしたり、回したりすると、肩が「ゴリゴリ」と鳴るような違和感が残りました。
特に気になったのが、腕を真横に伸ばし、手のひらを上に向けた状態から、腕を内側に捻って親指を床に向ける動き。このシンプルな動作で、肩の奥に明確な痛みを感じたのです。
「もしかして、これは肩のインナーマッスル、**ローテーターカフ(回旋筋腱板)**を痛めたのかもしれない…」 ネットの情報や自分の感覚から、そう推測するようになりました。
なぜ痛めた?考えられる原因と自己分析
どうして肩を痛めてしまったのか? トレーニングを振り返ってみると、思い当たる節がありました。それは、プレス系の種目、特にベンチプレスでの**「脇の開きすぎ」**です。
より重い重量を挙げたいという気持ちが先行し、肩関節に負担のかかるフォームになっていた可能性があります。脇が開くことで、肩の前方部分に過度なストレスがかかり、腱などが骨に挟み込まれる「インピンジメント」を起こしやすくなっていたのかもしれません。
試しに自宅で腕立て伏せをしてみると、脇をしっかり締めるダイヤモンドプッシュアップやナロープッシュアップでは痛みが出ませんでしたが、脇が開きやすいノーマルプッシュアップは怖くてできませんでした。このことからも、「脇の開き具合」が痛みの引き金になった可能性は高いと感じました。
また、ウォーミングアップはしていたつもりでしたが、それが質・量ともに十分だったかは疑問です。特に、ローテーターカフのようなインナーマッスルを意識した準備が足りていなかったのかもしれません。
肩の痛みの原因になりやすい部位ってどこ?それぞれの役割を知ろう
ここで、僕が痛めた可能性のあるローテーターカフも含め、トレーニングでの肩の痛みに関わりやすい主要な筋肉や組織について、少し詳しく見てみましょう。
- ローテーターカフ(回旋筋腱板):肩の安定を支える縁の下の力持ち
- どこ? 肩関節を深部で包む4つの筋肉(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)の総称。肩甲骨から上腕骨の付け根あたりに付着。
- 役割? 肩関節の安定化(最重要!)、腕の回旋、腕を上げる動きの補助。インナーマッスル。
- 日常では? 物を持つ、髪をとかす、着替えるなど、腕を使うほぼ全ての動作で肩を安定させている。トレーニングではこの安定性が崩れたり、腱が挟まれたりして痛めやすい。
- 三角筋:肩のパワーと見た目を司るアウターマッスル
- どこ? 肩全体を覆う大きな筋肉。前部・中部・後部に分かれる。アウターマッスル。
- 役割? 腕を前・横・後ろに上げる。肩を使ったパワフルな動きの主役。
- 日常では? 重い荷物を持つ、腕を高く上げる、物を押す・引くなど、力強い動きで活躍。トレーニングのメインターゲットだが、過負荷や悪いフォームで痛めることも。
- 上腕二頭筋長頭腱:肩の前を通る「力こぶ」の腱
- どんなもの? 力こぶの筋肉(上腕二頭筋)の腱のうち、肩関節の中を通る長い方。肩の前側の溝を通る。
- 役割? 肘を曲げる力を伝え、肩の安定にも少し関与。
- 痛みとの関連? 肩関節近くの狭い場所を通るため、使いすぎや炎症で痛みが出やすい。肩の前側の痛みの原因になることも。
- 肩峰下滑液包:骨と腱の間のクッション
- どんな組織? 肩の骨(肩峰)とローテーターカフの間にある薄い袋。潤滑液が入っている。
- 役割? 骨と腱の摩擦を防ぎ、スムーズな動きを助けるクッション兼潤滑剤。
- 痛みとの関連? 繰り返し圧迫されたり擦れたりすると炎症を起こし(滑液包炎)、痛みや腫れの原因になる。
鍛えるとカッコいい肩はどの筋肉?見た目と機能性の話
トレーニングをする上で、「見た目」もモチベーションの一つですよね。では、これらの筋肉のうち、鍛えることで男性として「かっこよく見える」のはどこでしょうか?
- 最重要は「三角筋」! 肩幅を広く見せ、丸みのある立体的な肩を作るには、三角筋の発達が不可欠です。特に中部を鍛えると横への張り出しが大きくなり、たくましいシルエットになります。Tシャツやジャケットも格段に似合うようになりますよ。
- 「上腕二頭筋」も忘れないで! 太く力強い腕の象徴である力こぶ(上腕二頭筋)も、かっこよさには欠かせません。
- 土台としての「ローテーターカフ」 ローテーターカフ自体は外から見えませんが、肩の安定性を高め、三角筋などを効果的かつ安全に鍛えるための土台となります。良い姿勢にも繋がります。
つまり、見た目のカッコよさを追求するなら三角筋と上腕二頭筋がメインになりますが、その土台を作り、怪我を防ぐためにはローテーターカフのケアと強化が非常に重要、ということです。バランスが大切ですね!
【最重要】自己判断は禁物!違和感があれば、まず専門医へ!
僕自身の経験からも強く言いたいのは、**「肩に痛みや違和感を感じたら、自己判断せずに必ず専門医(整形外科など)を受診してほしい」**ということです。
「たぶん〇〇だろう」「これくらいなら大丈夫」といった自己判断は非常に危険です。正確な診断なしにトレーニングを続けると、症状が悪化し、回復が長引いたり、取り返しのつかない事態になったりする可能性もあります。
専門医は、レントゲンやMRIなどの検査を通して、痛みの根本的な原因を突き止め、最適な治療法やリハビリ計画を立ててくれます。「休むのもトレーニング」ですが、それは医師の診断に基づいた適切な休養やリハビリであってこそ意味があるのです。
怪我を防ぎ、カッコいい肩を作るためにできること
今回の経験を踏まえ、安全かつ効果的にトレーニングを続けるために、以下の点を心がけましょう。
- 正しいフォームの習得: 特にプレス系では脇を締め気味に。自信がなければ専門家(トレーナーなど)に見てもらうのが一番です。
- ウォーミングアップの徹底: 肩全体のストレッチに加え、チューブなどでローテーターカフを刺激する種目も取り入れましょう。
- 適切な重量設定と休息: 無理は禁物。扱える重量で丁寧に。そして十分な休息で回復を促しましょう。
- 体の声を聞く: 痛みや違和感は重要なサイン。決して無視せず、トレーニング内容を見直したり、休んだり、専門医に相談したりしましょう。
まとめ:正しい知識で、安全にトレーニングを楽しもう!
トレーニングは素晴らしいものですが、怪我をしてしまっては元も子もありません。僕の体験が、皆さんが肩の怪我を防ぎ、長く安全にトレーニングを楽しむための一助となれば嬉しいです。
正しい知識を身につけ、自分の体と向き合い、そして何より、違和感があれば早めに専門医に相談する勇気を持つこと。これが、カッコいい体を作るためにも、健康を維持するためにも、最も大切なことだと僕は思います。

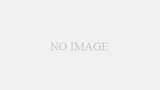
コメント