1. はじめに:ワインにハマり、数年越しの話題作を手に取った理由
こんにちは、ぽんきちです。
突然ですが、皆さんはワインはお好きですか? 実は私、すっかりワインにハマってしまいまして。それで、以前話題になっていたこの本を読んでみようと思ったんです。
それが、**『世界のビジネスエリートが身につける 教養としてのワイン』**です。
実際に手に取って読み始めたのは今年の4月。ちょうどワインへの興味が高まっていたタイミングだったこともあり、面白くて夢中になり、1週間ほどで読み終えてしまいました。
思い返せば、この本が最初に話題になった2018年頃、私はまだワインの世界に今ほど足を踏み入れていませんでした。
当時は、ワインを全く飲まなかったわけではないのですが、普段よく口にするのはビールや酎ハイ、カクテルといったお酒が中心。正直なところ、ワインに対しては「ちょっと難しい」「種類が多くてよく分からない」というイメージがあり、当時の私にとってワインは、「すっぱい」か「渋い」かの二択、くらいのイメージしかありませんでした。
周りのビジネスパーソンにワイン好きが多いのは感じていましたが、「ビジネスとワインの関係性って何だろう?」「なぜ特にワイン?日本酒じゃダメなの?」なんて素朴な疑問を持つ程度で、積極的に知ろうとまでは思っていませんでした。まさに、この本のタイトルにある「教養としてのワイン」という感覚は、当時の私には無縁だったのです。
そんな状態だった私が、今年(2025年)に入ってから本格的にワインを飲み始め、その魅力に開眼。
だからこそ、数年の時を経て改めてこの『教養としてのワイン』という本が、今の自分に何を教えてくれるのか、とても楽しみでした。ワインを「教養」として学ぶとはどういうことなのか? ビジネスシーンでどう活きるのか? そんな期待を持ってページをめくりました。
この本は、ワイン初心者だった頃の疑問と、ワインにハマり始めた今の知的好奇心の両方に、深く響く一冊となりました。
2. なぜエリートはワインを学ぶのか?本書が示す「教養」としての価値
本書を読んでまず腑に落ちたのは、ワインが単なるアルコール飲料ではなく、**歴史、地理、文化、経済と深く結びついた「教養」**であるという視点です。
例えば、フランスワインについて学ぶことはフランスの歴史や食文化に触れることであり、イタリアワインを知ることはイタリアの地域性や国民性を垣間見ることにも繋がります。このように、ワインはその土地の物語を内包しているのです。
そして、グローバル化が進む現代において、多様な文化背景を持つ人々と円滑なコミュニケーションを図る上で、ワインという「共通言語」がいかに有効か、という著者の主張には、深く納得させられました。相手の国のワインについて少し知っているだけでも、会話の糸口になったり、相手への敬意を示したりすることができるからです。
本書では、そうした考え方をベースに、主要なワイン産地やブドウ品種の基本、選び方、楽しみ方、そしてビジネスシーンでのスマートな振る舞い方などが、分かりやすく解説されています。
3. 読んで実感!知識がワインの味わいと会話を変えた体験談
本書を読んで、最も大きな変化は、ワインに対する自分の「感じ方」や「向き合い方」が変わったことです。不思議なもので、産地やブドウ品種、造り手の想いといった知識を持って飲むと、以前は単に「すっぱい」「渋い」と感じていたワインの味わいが、より複雑で奥行きのあるものに感じられるようになった気がします。これが「教養」ということなのかもしれません。知識が味覚体験を豊かにしてくれる、そんな実感がありました。
4. ワインは最高の「話すためのツール」だった
また、実利的な面で言えば、ワイン好きの方とのコミュニケーションが円滑になりました。ワインに興味がなかった頃は、ワイン好きの方が話す**「花の香りがする」とか「きのこや土のようなニュアンスがある」といった表現を聞いても、正直全くピンときていませんでした**。なんなら、よく分かりもしないのに相槌を打っていたこともあったかもしれません(それは単に酔っていて面倒くさかっただけかもしれませんが…まあ、それはさておき)。
しかし、この本で知識を得て、さらに自分自身もワインを楽しむようになってからは、そうした表現が何を指しているのか少しずつ理解できるようになり、ワイン好きの方との会話の引き出しが格段に増えました。以前は相槌専門でしたが、今では産地の話やブドウ品種の話で一緒に盛り上がれるようになり、話題が尽きません。
ビジネスシーンにおいても、その効果を感じることがあります。例えば、会食などで仕事の話が一段落したタイミングでワインが運ばれてくると、自然とワインの話題に移り、場が和んだり、スムーズに次の話題に移ったりする、そんなクッションのような役割も果たしてくれると感じています。一度ワインの話を挟むことで、場の雰囲気を変え、別の話に転換しやすくなるのです。
これらの体験を通して、ワインが持つ**『話すためのツール』としての力**、そして知識が体験を豊かにするという「教養」の本質を、私なりに解釈し、実感することができました。ワインは、単に味わうだけでなく、人と人とを繋ぎ、会話を生み出すための非常に有効な手段なのだと認識を新たにしました。
5. こんな人におすすめしたい!
この本は、特に以下のような方におすすめしたいです。
- 最近ワインに興味を持ち始めた、あるいはハマり始めた方(知識が体験を深めることを実感できます)
- ワインを通じてコミュニケーション能力を高めたいと感じている方(会話のきっかけや話題の転換に役立ちます)
- ワインについて基本から学びたいと思っている初心者の方(体系的に知識を得る良い入門書になります)
- (私の場合はまだそこまで実感は強くありませんが)グローバルなビジネスシーンで、ワインを通じて人脈を広げたい、あるいはスマートに振る舞いたいと考えている方
6. おわりに:ワインの世界への扉を開けてみませんか?
『世界のビジネスエリートが身につける 教養としてのワイン』は、ワインの世界への扉を開けてくれるだけでなく、グローバル社会で求められる「教養」とは何か、そして知識がいかに私たちの体験を豊かにしてくれるかを考えさせてくれる一冊でした。
数年前にただ「話題の本」として認識していた時とは違い、ワインへの興味が高まった今読むことで、より深く内容を理解し、その価値を実感できたように思います。
ワインリストを前にしても、もう以前のように尻込みすることはないでしょう。もちろん、すぐにソムリエのようになれるわけではありませんが、ワインとその背景にある物語に思いを馳せながら、コミュニケーションを楽しむ余裕が持てるようになった気がします。
ご興味のある方は、ぜひ手に取ってみてください。きっと、ワイングラスを傾ける時間が、より豊かで意味のあるものになるはずです。

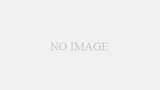
コメント